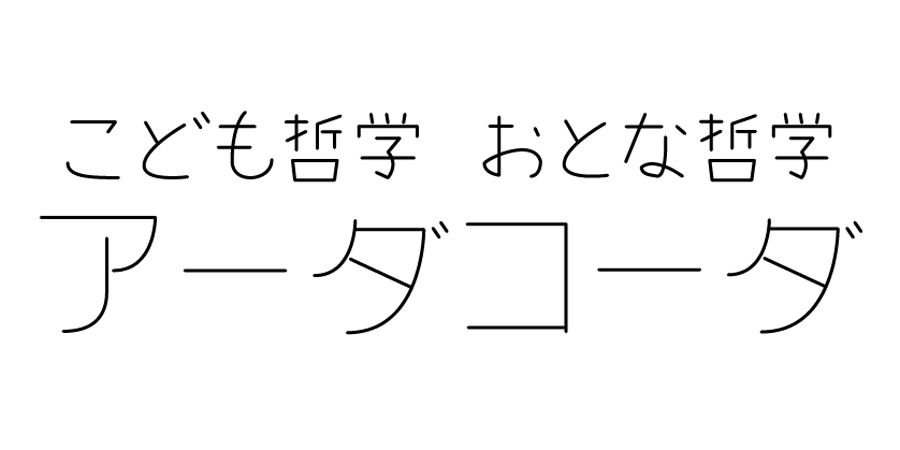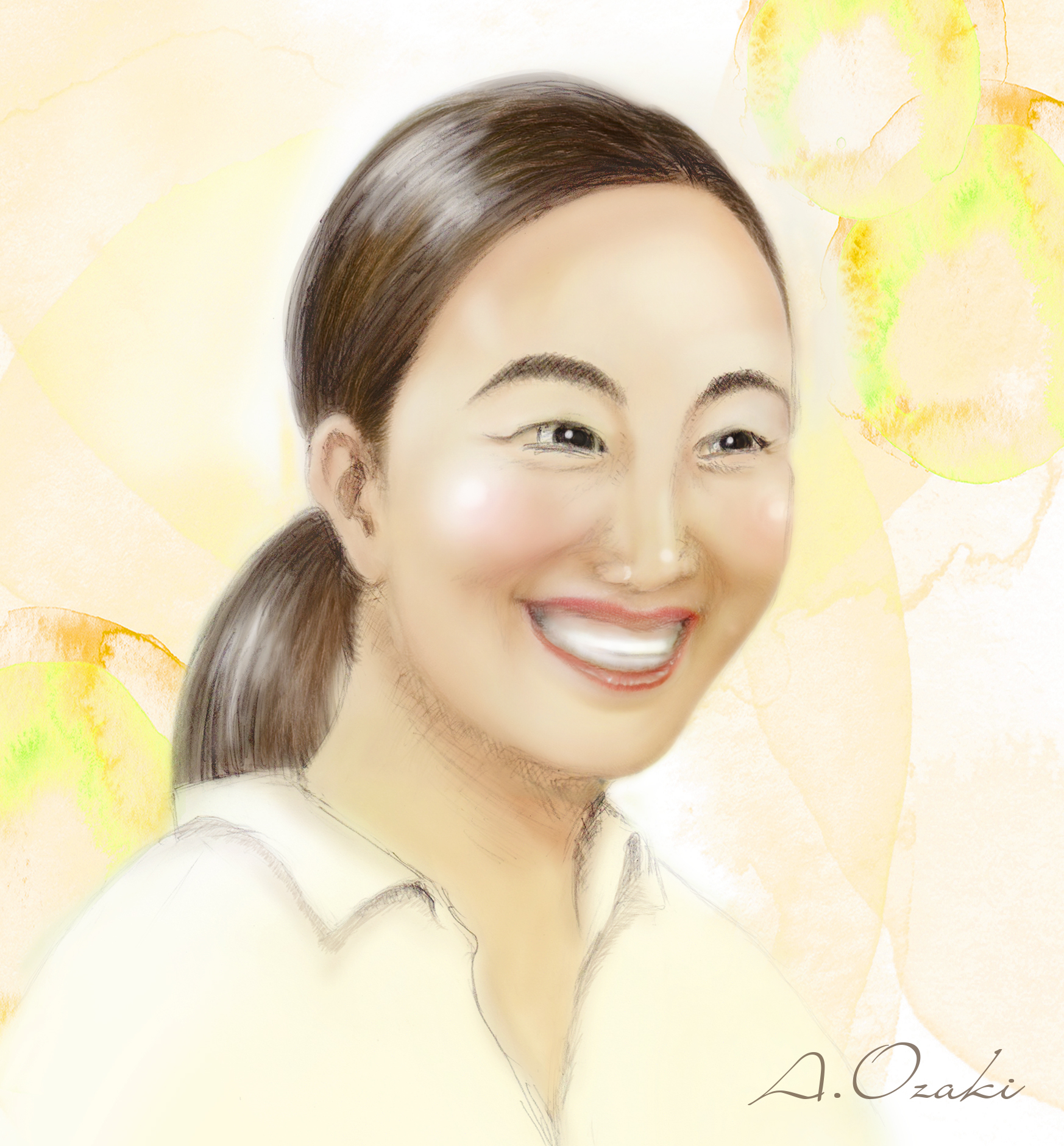角田 将太郎 (コーディネーター/講師/事務局スタッフ)

1995年生まれ。千葉県出身。県立船橋高校、東京大学教養学部卒業、東京大学大学院総合文化研究科修士課程在籍。哲学対話の実践と研究を往復しながら、互いに配慮し合いながら共に考える場をつくる方法について探究している。様々な学校や企業、自治体で講師の経験がある。
哲学するってなにがおもしろいの?
「あたりまえ」だと思っていたものが、実は「誰かにとってのあたりまえ」でしかないことに気がつく。そして、「あたりまえ」が「あたりまえだと思っていた何か」という抽象的な概念でしかないことに面食らう。さらに、地に足の着かない「あたりまえ」をじっと見つめ、手ざわりのある「新たなあたりまえ」へと作り変えていく。そんな一連の思考の更新過程とそこから生じる心の揺れ動きが心地よいです。
サイトをご覧の方にひと言
「心ってどこにあるんだろう?」が僕を哲学に引き込んだ最初の問いでした。みなさんはどんな問いをお持ちでしょうか。
河野 哲也 (講師)

立教大学文学部・教授。慶應義塾大学文学研究科後期博士課程修了、博士(哲学)。専門は哲学、倫理学、教育哲学。日本哲学会理事、日仏哲学会理事、日本科学哲学会理事、科学基礎論学会評議員など歴任。著書に 『「こども哲学」で対話力と思考力を育てる』(河出書房新社, 2014年)、S・ケイ、P・トムソン『中学生からの対話する哲学教室』(玉川大学出版部, 2012年, 共訳)、『意識は実在しない』(講談社メチエ, 2011年)、『道徳を問いなおす: リベラリズムと教育のゆくえ』(ちくま新書, 2011年)等。
哲学するってなにがおもしろいの?
肩の力が抜けて、たゆたう感じが味わえること。まじめに生きているけど、何となくどうでもいい感じもしてくること。人(とくにこども)と哲学対話していると、やられた、やられてうれしい、って感じがすること。
サイトをご覧の方にひと言
哲学をすると自由になれます。ぜひ、私たちと、ゆっくりとして、人の話を聞いて、うーんと考えて、何となく自分を変えましょう。
井尻 貴子 (コーディネーター/講師)
アート、哲学に関わるプロジェクト等の企画、運営、コーディネート、記録編集執筆などを行う。早稲田大学第一文学部(美術史)卒業、大阪大学大学院文学研究科(臨床哲学)博士前期課程修了。財団法人たんぽぽの家、公益財団法人東京都歴史文化財団東京文化発信プロジェクト室、NPO法人多様性と境界に関する対話と表現の研究所事務局長等を経て、現在に至る。共著書に、『哲学カフェのつくりかた』(大阪大学出版会、2014年)、『こども哲学図鑑』(あかね書房、2022年)、『こどもたちが考え、話し合うための絵本ガイドブック』(アルパカ、2023年)など。共編書に、『受容と回復のアートー魂の描く風景』(生活書院、2021年)などがある。
哲学するってなにがおもしろいの?
うーん、哲学するってなにがおもしろいの?の問いに答えるには、哲学するってなんだろう?ってことを考えなきゃいけない。それから、おもしろいってことも。それから、それから・・・だからすぐには答えられないけど、その予感は確かにあって、私をたすけてくれているような気がします。
サイトをご覧の方にひと言
ご覧いただき、ありがとうございます。いまご覧になっているあなたの関心は、どこにあるのでしょう?哲学?対話?こども?それとも、おとな? その関心を、疑問を、ぜひ伝えてください。一緒に哲学すること、はそこからはじまるのだと思います。
堀越 睦 (講師)

哲学カフェを主催する任意団体「さろん」の運営スタッフ。その哲学カフェにてファシリテーターを務め、月1度の哲学対話を楽しむ。本業はIT業界の会社員。2008年頃から「関東実験哲学カフェ」に参加者として通うが、同哲学カフェの閉会にともない、有志とともに「さろん」を立ち上げる。
哲学するってなにがおもしろいの?
それまでは全く関係ないと思い込んでいた二つの異なる概念の間に何らかの関係性を発見できる。「こんな簡単なことも分かっていなかったのかということに驚く。それらのことがまた次の発見や驚きを産み出していく。
サイトをご覧の方にひと言
「あのとき、あの人があんなことを言っていた」という印象に残る言葉の断片が、誰にも一つや二つはあるはずです。哲学対話では、そんな印象に残る言葉の一つに出会えるかもしれません。是非一度体験してみて下さい。
前田 有香 (コーディネーター/講師)
食品EC企業会社員、パラスポーツ団体職員・理事、立教大学文学部研究助手、パラスポーツの魅力発信を行うパラスポーツエバンジェリスト等の複業会社員。新卒で特別支援学校教員になり、2012年に障害者の社会参加や差別・偏見をテーマに、立教大学大学院文学研究科教育学専攻博士前期課程進学し河野哲也ゼミで哲学対話に出会う。在学中にパラスポーツに出会い、(公財)日本財団パラリンピックサポートセンターの職員を経て、2020年3月より現在のスタイルで活動中。
哲学するってなにがおもしろいの?
もやもやっとしていたことの形が少しずつ見えてくるところ。
言葉が自分のものになった、自分の想いが形になったような感覚を味わえること。
相手の心をのぞき見したようなワクワク感。
自分のことを見せることができた安心感と開放感があること。
サイトをご覧の方にひと言
忙しなく過ぎる毎日の中に、立ち止まってじっくり考える時間を作ってみませんか。
自分自身に、対話の相手に、こどもたちに対して、新たな発見があるかもしれません。
松本 弘子 (講師)

3人の年頃の娘をもつ母。埼玉県立がんセンターにて看護助手をしながら、2013年、人間総合科学大学(通信制)を卒業。卒業論文のテーマ「義務教育の中における、自己肯定感の持てる授業の提案」を考える中で、フランス映画「小さな哲学者たち」に出会う。現在は、リトミック教室を主宰する仲間とともに、幼稚園児~小学生とそのお母さんに向けた哲学対話や、性教育と哲学にまつわる地域活動を行っている。
哲学するってなにがおもしろいの?
「なぜ」と問うことから、とても自由な発想にジャンプ出来て、今まで眠っていた自分の細胞を使っていることが自覚できること。「沈黙」が怖くなくなり、「沈黙」に可能性を見出せるようになる。
サイトをご覧の方にひと言
こども哲学教室の中でのこどもたちは、自分の感じたことを無意識な規制を働かさないで率直でストーレートな意見を発表してくれることがあり、その素直な意見に感動し、自分の中の余計な既成概念をお掃除していくことができます。
寺田 俊郎 (講師)

上智大学文学部哲学科教授。京都大学大学院文学研究科博士後期課程(哲学)学修退学、2001年大阪大学大学院文学研究科博士後期課程(文化形態論)単位取得退学、2004年同修了(文学博士)。1992年~1998年洛星中学・高等学校教諭、2001年~2010年明治学院大学助教授・准教授、2010年より現職。主な研究分野は近現代の実践哲学、臨床哲学。カフェフィロ会員。
哲学するってなにがおもしろいの?
いつでもどこでもすることができ、何でもテーマにすることができ、何度でもやり直すことができるところ、つまり自由なところ。それから、他の人々と対話しているうちに、自分の考えが変わっていく経験。
サイトをご覧の方にひと言
一人一人が生きるなかで出会う問いを、自分で考え、他の人々と対話しながら考えること、それが哲学。一緒にやってみませんか。
小川 泰治 (講師)

宇部工業高等専門学校一般科(社会)講師。早稲田大学大学院文学研究科哲学コース博士後期課程満期退学。中学・高校・専門学校で「倫理」や「現代社会」、「哲学対話」の非常勤講師を務めたのち、2018年4月より現職。分担執筆に『こころのナゾとき 小学1・2年/ 小学3・4年/ 小学5・6年』(成美堂出版、2016年)など。子どもの哲学についての論文に「「子どもの哲学」における知的安全性と真理の探究 ― 何を言ってもよい場はいかにして可能か」(『現代生命哲学研究』、2017年)などがある。
哲学するってなにがおもしろいの?
誰も最終的な答えがわかっていないような「問い」を前にして真剣に考えていると、子どもも、大人も、偉い人も、そうでない人も関係なく、みんなが「哲学すること」の前でフェアになれるような瞬間があること。
サイトをご覧の方にひと言
「哲学してみたい!」と思ってもなかなか一人ではいつ、どうやってやったらいいかもわからず踏み出せないこともあると思います。ですが、普段話さないだけで周りにも考えることが好きな人たちはいるものです。まずは私たちと一緒に「哲学すること」の不思議で楽しい世界へと入っていきませんか?
天野 美和子 (講師)
東海大学児童教育学部児童教育学科の教員。博士(子ども学)。元私立幼稚園教諭。保育内容の「人間関係」や「幼稚園教育実習」「乳幼児心理」「シティズンシップ(現代社会と市民)」などの授業の他、保育者向けキャリアアップ研修も行っている。カナダの親教育プログラムNobody’s Perfect Japan認定ファシリテーターとしても活動している。共著に『園づくりのことば:保育をつなぐミドルリーダーの秘訣』(丸善出版)、『乳幼児の発達と保育』(朝倉書店)、『子どもの理解と保育・教育相談[第2版] (新時代の保育双書)』(みらい)、『マルチステークホルダーの視座からみる保幼小連携接続:その効果と研修のあり方』(風間書房)などがある。
哲学するってなにがおもしろいの?
日々の生活の中で出会う素朴な問いについて深く深く考え続けてみると、「正解などないんだ」ということに気づきます。それを心の底から実感できたとき、なぜだかフッと気持ちが軽くなります。何とも言えない解放感のようなものが得られて心地よいです。おもしろいと言えば、小さな子どもの何気ない呟き。そこに子どもたちの哲学的なセンスを感じてハッとさせられることがあります。
サイトをご覧の方にひと言
アーダコーダの哲学対話に出会ってから、私にとって哲学が身近に感じられるようになりました。以前は、著名な哲学者の思想についての知識がないと哲学できない、哲学してはいけないのではないかと思っていました。でも、哲学的な問いは私たちの日常のなかに沢山あって、大人だけではなく、すでに幼児期の子どもにも哲学的な思考が芽生えていることに気づきました。頭の中を柔らかくして、是非ご一緒に哲学対話を楽しみましょう!
桑原 眞理子 (コーディネーター/講師/事務局スタッフ)

大学卒業後、食品メーカーを中心に商品開発·マーケティング職に従事。「こども哲学」との出会いをきっかけに、子どもの斬新な発想に魅せられ2018年に独立。子どものマーケティング思考を育む体験型キャリア教育プログラム「こどもマーケター入門」を開発し、ワークショップ等を実施。現在はモンテッソーリ教師として教室を運営する傍ら、主に幼児〜小学生・保護者を対象とした哲学対話のファシリテーターとしても活動。モンテッソーリ教室 マヴィのおうち 主宰。日本モンテッソーリ教育総合研究所認定 3-6歳教師。保育士。
https://www.ma-mavie.com/
哲学するってなにがおもしろいの?
今までの何気ない思い込みに気づけ、新しい世界が開ける感覚がなんとも心地よいです。
特に、子どもたちからの学びは計り知れないものがあります。
サイトをご覧の方にひと言
小さな子どもたちと哲学対話をして、マーケティングの仕事に通じるものを感じました。むしろ、子どもの方が純粋に顧客満足を追求できるのではないかとすら…。子どもたちも含めた多様な人たちと哲学対話することは、ビジネスでブレイクスルーのヒントになるかもしれませんよ。
鳥羽瀬 有里 (コーディネーター/講師/事務局スタッフ)
上智大学心理学科卒業後、外資系コンサルティング企業にて主に金融関係のプロジェクトに従事。その後欧州系コンサルティング企業の立ち上げに参画。人事関連の責任者として、社員ひとりひとりのキャリアを見据えた新たな評価、育成制度を構築。現在はポートフォリオワーカーとしてあらゆる職種業種の仕事に携わりながら2児の男子を子育て中。
哲学するってなにがおもしろいの?
頭の中に「?」を持つことが日常になっていくこと。いろんな日常に対して新たに「?」を持てるようになることで、目の前の景色が変わって見える。「あたりまえ」も「ふつう」もなく、探求心こそが、考えることこそが、人生の面白みだと気付けること。
サイトをご覧の方にひと言
目の前にあるものをまず静かにゆっくりと見つめて、何かあなたのなかに「?」を浮かべてみることから始めませんか?企業でも、家族でも、一人でも、「?」を考えることが、きっと私たちを自由にしてくれます。
幡野 雄一 (コーディネーター/講師)

高校卒業後、ヒッチハイキング、野宿生活、四国の歩き遍路などを経験。その後、駒澤大学仏教学部禅学科に入学し、学部を首席で卒業。卒業後は、学校、塾、地域などで、様々な世代の人たちと哲学対話を行う。2018年、走る小屋とテーブル「ポイトラ」の運営を開始し、各地で哲学対話を企画。2019年、国立駅北口に探究型学習塾「ベースクール」を開校。
哲学するってなにがおもしろいの?
なにがおもしろいんだろう?ちゃんと答えようとするとわからなくなっちゃうなぁ・・・あっ!わからなくなって良いのも哲学のおもしろさだ。あれ?でも、なんでわからなくなって良いとおもしろいんだ??本当にそれは「おもしろい」なのか???んー・・・。こんなことをみんなで語り合えるのが哲学のおもしろさかも!!
サイトをご覧の方にひと言
「わからない」に正直になると、スッと気が楽になります。力みすぎず、急ぎすぎず、ゆったり、じっくり、語り合い、考える時間。たまにはそんな時間を過ごしてみませんか。
盛岡 千帆 (コーディネーター/講師/事務局スタッフ)
2016年よりこども哲学の研究・実践をはじめ、修士号(教育学)を取得。小学校教諭、中学校教諭(英語)、高校教諭(英語)の免許所持。その後、株式会社LITALICOに入社し、幼児〜小中高生の発達支援やIT×ものづくりのサービスに携わる。現在は、学校、企業、美術館、地域などでこども哲学ファシリテーターを務めている。福島県立ふたば未来学園中学校・高等学校 哲学対話(道徳)特任講師。共編書に『こどもたちが考え、話し合うための 絵本ガイドブック』(アルパカ、2023年)、『Prácticas filosóficas comparadas ―Filosofía con/para niños. Consultoría filosófica. Talleres filosóficos―』(noveduc、2019年)がある。
哲学するってなにがおもしろいの?
哲学しているときは、あらゆることを「疑う」ことから始められること。自分や他者の当たり前を「それって本当かな?」と面白く問うことができること。答えを出すことを目的とせず、思考を深めていくことを楽しめること。
サイトをご覧の方にひと言
私にとって、哲学することは遊ぶことです。遊びの中で思いもよらないアイデアを発見することが何よりも楽しく感じます。哲学することを通して、自分の中の「こだわり」を一度手放し、日常生活での自分とは少し違う、「哲学モードの自分」も手に入れてみませんか?ぜひ一緒に哲学しましょう!
尾崎絢子 (講師)

はなこ哲学カフェいどばたのいどほり主宰。保育士・幼稚園教諭。2014年より学校や保育園、地域など様々な場所で大人や子どもと対話する場作りをしている。幼児期の子どもや子どもの支援者(子育て中の保護者や保育士など)のための対話を実践の軸にし、2021年より都内のこども園にて、園全体に哲学対話を導入・設計・実践・研究する講師として参画。
哲学するってなにがおもしろいの?
哲学をしていると、遠い昔、どこかでなくしてしまった大切な何かを見つけたような、そんな感覚に出会うことがあります。自分の中で思い込んでいた価値観が、他者の何気ない一言によって揺らがされたとき。誰かや何かに奪われていた問いが、哲学することによって取り戻されていく瞬間に立ち会うとき。哲学するって本当に豊かな営みだなあと感じます。
サイトをご覧の方にひと言
哲学することは私たちの日常の「半径2メートル」にあります。あなたの足下にある小さな問いを、1人ではなく、ぜひみんなで一緒に考えてみませんか?みんなで一緒に考えることで思いもよらない発見があるかもしれません。
ふなやま まい (講師)
アーダコーダ講座修了生。本業は会社員。 2018年頃からアーダコーダの美術館、幼児、小学生、高校生向け哲学対話の場を経験。生活クラブで「親子で楽しむ!こども哲学」を担当。
哲学するってなにがおもしろいの?
日常のなかで感じていること、思っていることを意識的に考えるうちに、なんでそう思うんだろう…と前提が揺さぶられる瞬間があること。
サイトをご覧の方にひと言
「人の話を最後まで聞く」「わからないことを質問する」「自分の考えを素直に言う」など、年を重ねるほど難しく感じます。哲学対話を通して、自分も他人も尊重しながら話し、聞き合う心地よさ・楽しさを取り入れてみませんか?
安本志帆 (講師)
元幼稚園教諭。コミュニティや組織、学校の中に入り長期継続的な関わりをしている哲学対話実践者。愛知県犬山市を拠点として活動している「犬てつ(犬山×こども×大人×てつがく×対話)」の歩みを書籍とした『こどもと大人のてつがくじかん てつがくするとはどういうことか?』も販売中。(社)未来の体育を構想するプロジェクト理事(社)日本科学振興協会理事
哲学するってなにがおもしろいの?
おもしろいと思えるかというと実は私はそうでもありません。哲学をすると逃げられないからです。とても苦しい答えを導き出してしまうことも多々あります。ただ、きれいに反転して考えられた時や、他者と共に激しく哲学の議論ができた時には「おもしろい」と感じているかも?!
サイトをご覧の方にひと言
アーダコーダから始まった私の「こどもと大人とのてつがく時間」は私の人生においてかけがえのない時間となりました。ぜひ皆さまとご一緒できますことを楽しみにしております。
和佐陽子 (講師)

私立中高一貫校の英語科非常勤講師、観光分野のマーケティングディレクター。大学では国際関係を学び、渉外法律事務所にてパラリーガルとして勤務した後、英語教員となり中高の英語教育に携わっている。また、大学院の観光科学コースにて訪日外国人の観光やまちづくりを研究し、2014年から観光マーケティングの分野にも関わる。教員生活、子育て中に模索するうち哲学対話に出会い、アーダコーダのファシリテーター養成講座を修了。ファシリテーターとして対話の場に携わっている。
哲学するってなにがおもしろいの?
自分にとって「あたりまえ」と思い込み、こだわってきたことが、対話をする中でガラガラと崩れていったことがありました。反対に、対話をするうちに、かえってわからなくなることも。でも、そのこと自体を受け入れていいんだ、と自由になれたり。そんな体験がおもしろい、と感じます。
サイトをご覧の方にひと言
「哲学」x「対話」と聞くと、身構えてしまった方がいらっしゃるかもしれません。でも、「哲学対話」は、もっと気軽で、身近なところにあって、ものの見方、考え方をラクにしてくれる力を秘めていると思っています。ぜひ体験してみてください。
大前みどり (講師)

人材育成や起業支援の会社で働いた後、独立。組織、学校、地域、コミュニティが、内側から活性化していくための対話の場づくりを行っている。様々な対話の場に携わるなかで、特に哲学対話の魅力や可能性を実感し、毎月の哲学対話の他、進行役向けのトレーニングや探究講座を主催している。ダイナミクス・オブ・ダイアログ合同会社代表。経営管理修士(MBA)。
哲学するってなにがおもしろいの?
日常のなかで見過ごされてしまいそうないろいろなことの「そもそも」について、立ち止まって、時には後戻りしながら、ゆっくりじっくり考えられること。自分がいつの間にか持っていた「当たり前」に気づいて、「どうして自分はそう思い込んでいたのだろう?」と愕然としながらも、そこから自由になれること。
サイトをご覧の方にひと言
哲学対話では、どこから考えたらよいのかわからない途方に暮れてしまうような大きな問いも、そんなことも哲学できるんだという何気ない問いも、お互いの意見を聴き合い、問いかけ合いながら探究していくことができます。「へえぇ」「なるほど~」」の連続です。そのおもしろさをぜひ一緒に味わいませんか?